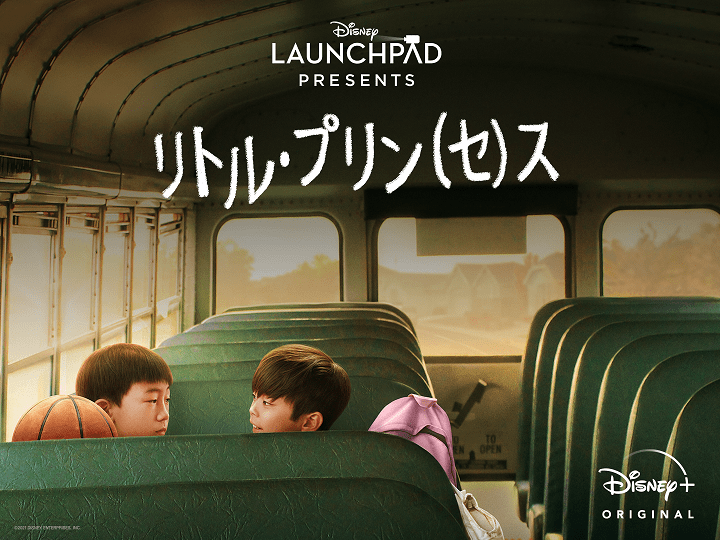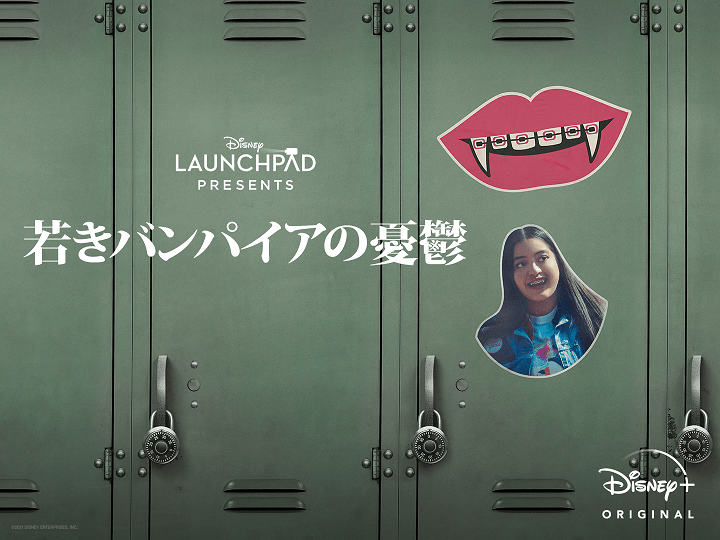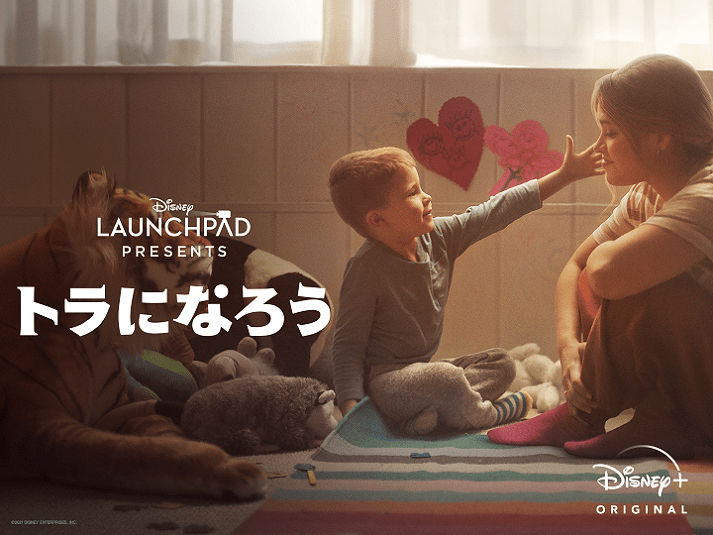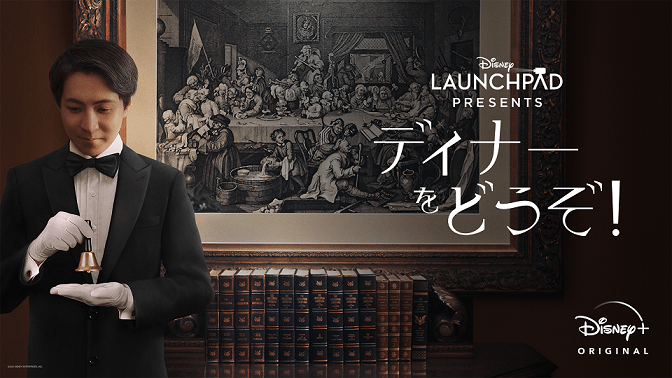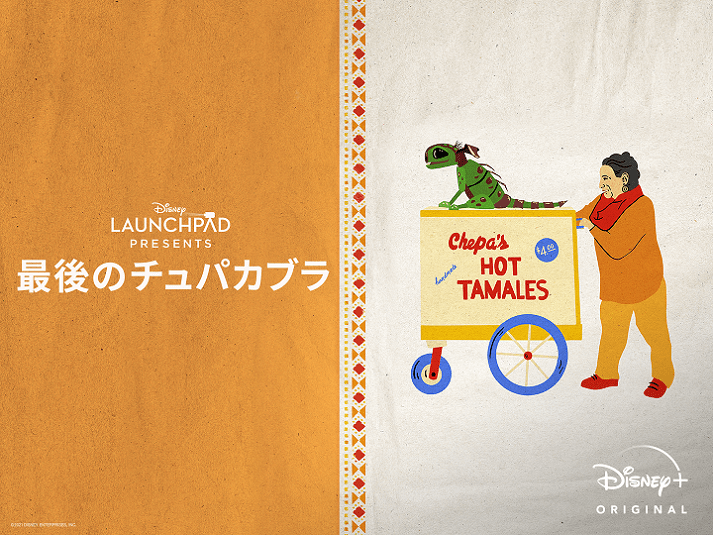ディズニーやディズニー&ピクサー、マーベル、スター・ウォーズ、ナショナル ジオグラフィックの映画作品、TVシリーズやディズニープラスのオリジナル作品が見放題のディズニー公式動画配信サービス「Disney+(ディズニープラス)」
今回は、ディズニーが新世代の若き映像作家たちを支援するプロジェクト“Disney Launchpad”から生まれた短編映画6作品をまとめて紹介していきます☆
ディズニープラス “Disney Launchpad"プロジェクト「短編映画6作品」
配信開始日:2021年6月4日(金)よりディズニープラスにて独占配信スタート
様々なバックグラウンドを持つ新世代の若き映像作家をディズニーが発掘・支援し、彼らのユニークな視点で描いた短編作品を世界配信する「Disney Launchpad」
まさに“Launchpad(=発射台)”となるようなプロジェクトです。
それぞれの映像作家たちをディズニープラスはもとより、マーベルやピクサーなど映画製作の第一線で活躍するエグゼクティブが制作をサポートしています。
第1弾となる今回のテーマは「発見」
選ばれた6人の若き映像作家によってユニークな視点で描かれる、多様性、創造性豊かな約20分のオリジナルストーリーです。
配信作品は、バレエや人形遊びが好きな中国人の少年との友情の物語『リトル・プリン(セ)ス』、人間とバンパイアの間に生まれた少女の悩みをコミカルに描いた『若きバンパイアの憂鬱』
母親を亡くした主人公が、4歳の子供の子守をするうちにその悲しみを乗り越えていく様子を描いた『トラになろう』
その他にも、それぞれ多様な生き方や価値観を反映しながらも、前向きで人とのつながりを感じられる全6作品が登場します。
誰しもが持っている“自分らしさ”を大切にすることの意味。
そして自分とは異なる他者を理解し尊重し合う事の大切さが一人ひとりの心に響く、希望溢れる珠玉の短編映画をまとめて紹介していきます☆
『リトル・プリン(セ)ス』
監督:モキシー・ペン氏
バレエが⼤好きな7歳の中国⼈の少年・ガブリエルと、同じ⼩学校に通う中国⼈のロブは友達になります。
しかし、ロブの⽗はガブリエルの「⼥の⼦らしい」⾔動に疑問を⽰し、2⼈の友情を引き裂こうとします。
監督を務めたのは、中国湖南省出⾝の脚本家・モキシー・ペン氏。
労働者階級の⼈々、少数⺠族の移住者たち、そしてクィア(男性にも⼥性にも分類されない性別認識)・コミュニティの⼈々の⽇常を映像化しています。
――”Disney Launchpad” に選ばれた時、どう思いましたか?
モキシー・ペン監督(以下、敬称略):僕は最初、何人の人が応募したか知らなかったんです。
僕は当時、ニューヨーク大学のフィルムスクールの最終学年でした。仕事を探していてロサンゼルスに引っ越そうか考えていました。
そこで“Disney Launchpad”のことを知り、応募してみようと思いました。
この経験は本当に素晴らしいものでした。ただ、僕はディズニー的なストーリーを語ろうとしていたわけじゃありません。
ただ、自分の心にとても響くストーリーを、僕にとって意味があるストーリーを語りたかっただけなんです。
なので、僕が子どもの頃に起きたことを思い出しました。そして、僕の人生に基づいたストーリーを書きました。
――この映画のアイディアをどのようにして思いついたのですか?
モキシー・ペン:僕にとって『リトル・プリン(セ)ス』は、子供の頃、中国で育った僕の人生経験を基にしているから、とても大切な物語です。
僕は5歳で、ガブリエルみたいな子でした。とてもフェミニンなものや、ピンク、プリンセスに夢中でした。
そんな中、近所にいる少年と友達になりました。彼の父親は僕たちの仲を疑い始めて、僕が彼に悪い影響を与えているのだと思い始めました。
ある日、彼は夕飯の時間にやってきて、僕の父に、「モキシーは普通の子供じゃないから矯正する必要がある」と言いました。
僕は家族をがっかりさせてしまったと思い泣きました。けれど父はとても怒って僕の味方をしてくれて、僕のために立ち上がり、「あるがままの息子を愛している」と言ってくれたんです。
もし僕が、本やプリンセスが好きならそれで構わないって。それから父は、「大体、あなたの子供は好きじゃない」と言ったんです。もちろん、最後の部分は映画には入れませんでしたよ。
僕はそのことをとてもよく覚えています。なぜなら、言葉が人を傷つけることがあるということに気がついた、初めてのことだったからです。
僕はまた、あるがままの僕を受け入れてくれる人がいることにも気づきました。
僕はそのメッセージをずっと持ち続けていて、Disney Launchpadのプロジェクトを知った時、それをストーリーに入れ込んで、クイアやトランスジェンダーの子供たちは独りじゃないということを表現したかったんです。僕たちはいつも彼らのことを気にかけています。僕たちはいつもお互いのことを助け合っているんです。
――撮影はいかがでしたか?
モキシー・ペン:最も大変だったところは、ディナーのシーンの再現です。主人公ガブリエル役のケイロ・モスは、そのシーンで涙を流さなくちゃいけなかったからなんです。
たまに涙を流すのに時間がかかる時があります。その時はとても神経がすり減りました。
なぜならコロナ禍の間に撮影していたから、時間がかかった分、すべての食べ物を温め直す必要があったんです。
そして、人がいなくなった後は、すべてのものにカバーをかけないといけなかった。その対処にはかなり時間がかかりました。
みんなが、彼が上手く演技を出来るのかどうか、とても不安だったと思います。でも幸運なことに、彼はうまく出来たんです。とても素晴らしかったです。
――この映画のテーマやメッセージは何でしょうか?
モキシー・ペン:この映画を見て、広い心を持ち続けるようにして欲しいと思います。そして、トランスジェンダーやクイアの人たちに興味を持ち、信頼して欲しいです。
彼らは実際にここに存在する人間なのですから。
『若きバンパイアの憂鬱』
監督:アン・マリー・ペイス氏
メキシコ系アメリカ⼈で、半分⼈間・半分バンパイアのヴァル・ガルシアは、⼈間の世界でもモンスターの世界でも⾃分の正体を隠しています。
しかし、⼈間の親友がモンスター学校に迷い込んできてしまい、ヴァルは⾃分⾃⾝と向き合うことを決意します。
監督のアン・マリー・ペイス氏は、テネシーで⽣まれ育ち、現在はロサンゼルスを拠点に活動する脚本家/監督。
メキシコ系アメリカ⼈で、決められた型に収まらない⼼の在り⽅を描くストーリーや多⽂化の視点からストーリーを描きます。
――あなたがDisney Launchpad” に選ばれた時のお気持ちをお聞かせください。
アン・マリー・ペイス監督(以下、敬称略):とても素晴らしい瞬間でした。人生が変わるような経験になることがわかっていたけど、どれほど変わるのかということには気づいていませんでした。
このプログラムはそれほどにスペシャルだったんです。皆さんはとても愛に溢れていて、制作期間を通してずっと、私の家族のように感じられました。
私がストーリーを語る手助けをしてくれたし、とても励ましてくれました。間違いなく、人生が変わるような経験でした。
――この映画のアイディアをどのようにして思いついたのですか?
アン・マリー・ペイス:『若きバンパイアの憂鬱』のストーリーは、半分人間で、半分バンパイアの女の子(ヴァル)について描いています。
私はメキシコ系アメリカ人で、バイセクシュアルなんです。だから子供の頃、2つのアイデンティティの間にいるように感じて、これらのアイデンティティのどこに属しているのかはっきりわからなくて、とても苦しみました。
私はそういうことをヴァルを通して掘り下げたかったんです。そして、私が人生の後半になって気づいたことに彼女が気づくようなジャーニー(旅)に連れて行ってあげたかったんです。
それは、あなたが複数のアイデンティティを持つ人だからといって、あなたはそのアイデンティティのごく一部だということを意味していないということです。そのアイデンティティの全てが、あなたがどういう人かということを作り上げて、完璧な人間にしているのだって気づかせてあげたかった。
ただ、私と違って、彼女がメキシコ人でクイアであることを讃えたかったので、それが葛藤にならないようにしました。
代わりに、バンパイアの要素を葛藤にしました。モンスターはいつも恐れられたり、誤解されていて、アウトサイダー的な側面がありますよね。そんなアウトサイダーとしてのモンスターは、私たち誰もが感じてきた疎外感を体現できる存在だと思いました。
――VFX等が使われている大作ですが、撮影はいかがでしたか?
アン・マリー・ペイス:すべての要素が、私がこれまでに撮影した中で一番困難なものでした。コロナ禍ということで、映画スタッフがしなくてはならない特別な予防策があって、事前に計画したり、考えないといけなかったんです。
でも、その過程でディズニーにサポートしてもらえるのは素晴らしかったです。ディズニーのキャスティング部、音楽部、VFX部のみんなが力を合わせて、私たちを助けてくれました。
そしてディズニーのみんなは、これらのとてもユニークなストーリーを多様な視点で語るというこのプログラムの成功を信じてくれていました。
だから私は、このビジョンを実現させるために、ディズニーのすべての部門の人たちによって支えられているのだと感じました。
――この映画からどんなことを受け取ってもらいたいですか?
アン・マリー・ペイス:私はずっと日本文化が大好きでした。私が是非行ってみたいと思っている場所のひとつです。このストーリーの見どころは、日本の皆さんからすると、全く違うバックグラウンドから来ているというところです。
このストーリーを観ることで、皆さんに受け取ってもらいたいことは、恥ずかしいと思っていたり、隠すようにと言われてきたどんな部分も、実はあなたを支えるスーパーパワーだということです。
それらは、皆さんの人生に彩りを与えてくれます。とてもスペシャルなんです。
だから、この映画を観た後、人々は、あるがままで完璧だということに気づき、そういうところに強さを見つけてくれればいいなと願っています。
『トラになろう』
監督:ステファニー・アベル・ホロヴィッツ氏
⺟親を亡くした悲しみを乗り越えられないアヴァロン。
4歳の⼦供の⼦守をするうちに、意外にも悲しみが少しずつ癒やされていく物語です。
『トラになろう』の監督は、10年間舞台の演出をした後、映画に転向したステファニー・アベル・ホロヴィッツ氏。
彼⼥の2作目の短編映画『SOMETIMES, ITHINK ABOUT DYING』は、2019年サンダンス映画祭で初上映され、アカデミー賞の選抜候補名簿にも残りました。
――素晴らしい映画でしたね。Disney Launchpadに選ばれていかがでしたか?
ステファニー・アベル・ホロヴィッツ監督(以下、敬称略):これはクレイジーだと思いました。すごく興奮したし、とてもワクワクしました。これは参加するのにとても素晴らしいプログラムでした。
私たち6人のフィルムメイカーたちにとって、私たちのキャリアで初めて、大きなスタジオ映画を作れるチャンスでした。
さらに、その製作過程でとても支援して頂きました。こうした大きなキャリアの経験を積ませてもらっている間、ディズニーの一員になれたことは、本当に素晴らしいことです。
――あなたはこの映画のアイディアをどのようにして思いついたんですか?
ステファニー・アベル・ホロヴィッツ:私の祖父母は100歳になろうとしていました。そして私の両親は70歳になろうとしていて、一方で甥は4歳になるところでした。私はそれを見て、人生のバトンを渡すということを考えました。
私は、20代の始めのころ、ベビーシッターをしていました。その子は4歳くらいの男の子で、頭が良くて優しい子でした。でもある日、彼は指を銃の形に構えて、私を撃ち殺そうとしました。それで私が「それがどういう意味か知ってるの?」と聞いたら、彼は知らなかったんです。
だから私は「もし私が死んだら、私はもうここに来れなくなるの。私たちは遊べなくなるんだよ」と言いました。そうすると、男の子はとても悲しんでいました。
それを通じて、私は「私たちはみんな、いずれ死ぬという悲劇を背負っている。だから私たちは、痛みや喪失感に何度も何度も苦しまないといけない。私たちは自分たちの文化の中で、そのことについてどうやって話すのだろう。どうやってそれを分かち合い、子供たちに伝えていくのだろう」と考えるようになりました。実はそれは、私が得意じゃないことなんです。
私の両親はセラピストだから、私は話を聞くことは得意だけれど、自分の悲しみや弱いところを他の人と分かち合うことが上手くできないんです。
だからこそこの映画は、そういった自分自身の弱い部分を分かち合い、自分の人生で出会う人々への贈り物だということを描いています。それは、この世界や、痛みの中で、あなたは独りじゃないということを覚えておく方法なんです。
――撮影はいかがでしたか?一番のチャレンジとなったのはどんなことでしょうか?
ステファニー・アベル・ホロヴィッツ:コロナ禍のことが大変でした。コロナ禍の中で、監督する機会を得られたのはとても素晴らしいことです。
でも、映画作りで私が大切にしたいのは、コミュニティなんです。すごくたくさんの人々が一緒になって同じプロジェクトの仕事をして、そして協力しあって、同じ問題に向き合うんです。
コロナ禍の中でも、私たちはコミュニケーションが取れたけど、6フィート(1.8メートル)以上近づくことが出来なくて、PPE(個人用防護具)を身につけないといけないのは、現場でのコミュニケーションに間違いなく障害となりました。
だから、私たちみんなが安全な状態になってワクチン接種をした後で、また現場に戻れるのを楽しみにしています。
――日本のみなさんにメッセージをお願い出来ますか?
ステファニー・アベル・ホロヴィッツ:皆さんが気に入ってくださることを願っています。
この映画が、皆さんにとって何らかの意味があればいいなと思います。
それがある意味、心を動かす経験になって、誰か他の人と、思いを分かち合いたいと思ってくださることを願っています。
『ディナーをどうぞ︕』
監督:ハオ・ズン氏
全寮制のエリート学校に通う中国⼈留学⽣。
彼は、まだ留学⽣が誰も採⽤されたことがないリーダー役の試験に挑戦し、努⼒ではその役を勝ち取れないと気付きます。
エマーソン⼤学(映画制作)、およびAFI(監督)で学んだ、監督のハオ・ズン氏。
⼈気のある中国の映画やテレビ番組に出演するプロの俳優から、学⽣アカデミー賞受賞監督に転⾝した映像作家です。
――”Disney Launchpad” に選ばれた時、どう思いましたか?とても競争率が高かったですね。
ハオ・ズン監督(以下、敬称略):そうですね。僕は、選ばれてものすごく幸運だと思いました。選ばれたことがわかった日を今も覚えてます。
僕はロサンゼルスのコーヒーショップに座っていて、そしたら、ディズニーから電話がかかってきたんです。彼らが優しく話しかけてくるから、それで「僕は選ばれなかったんだ」って思ったんです。
だって最初にそうやって人を褒める時って、大抵「けれども…」って続くでしょ?
でも、その後に彼らは「あなたはDisney Launchpad プロジェクトにもう入ってますよ」って言ったんです。僕は「ワオ!」って感じで、文字通り5分間くらい固まってしまいました。
子供の頃、僕はたくさんのディズニー映画やヒーロー映画を観て育ったんです。僕自身、スーパーヒーローになりたかった。
だから、このプロジェクトに参加することは、僕にとってとても大きな意味があることでした。
――この映画のアイディアをどのようにして思いつきましたか?
ハオ・ズン:『ディナーをどうぞ!』は、アメリカのエリート寄宿学校の中国人の学生が、これまで留学生が一度も申し込んだことがない、リーダーシップのポジションに申し込もうとすることについて描いています。それは、僕が初めてアメリカに来た時の僕自身の経験にかなり基づいているんです。
僕は当時15歳で、ニューヨークの高校に通ってました。最初アメリカに着いた時、誰も僕のことを見てくれなかった。だから、注目されたくて色んなポジションに応募したんです。
でも次々と失敗しちゃって、最終的に残ったものがダイニングルームのメートルディー(接客主任)でした。
それはディナーの始まりのアナウンスをする係で、毎晩ディナーの間、みんなに見られるポジションなんです。
僕の英語の発音は良くなかったし、30テーブル分の生徒の名前を暗記するのはとても大変でした。頑張ったけど、テストが重なったこともあって、なかなか上手くできなかったんです。
僕は凄くプレッシャーを感じてしまって、そのままステージに上がって中国語で歌を歌いました。ぎこちなかったし、中国語だから誰も歌の内容を理解できなかったけど、でも僕はとても満足でした。
それが僕が本作で描きたかったストーリーなんです。たとえぎこちなくても、たとえ誰も理解しなくても、僕たちは自分自身の声を聴かなきゃいけないんです。
――撮影はいかがでしたか?この映画を撮影していて最も大変だったのはどんなことでしたか?
ハオ・ズン:この作品が、コロナ禍で製作に入った最初の映画でした。その当時、コロナ禍の時に撮影するのがどういうことなのか、まだ誰もわかっていなかったんです。
みんながそれに対応しようとしていて、撮影できる時間が凄く限られていました。
だからショットを削除したり、ショットを組み合わせたりする必要があって、とても大変でした。
また、常にフェイスシールドやマスクをつけていないといけなかったんです。どうやって役者たちとコミュニケーションを取れば良いのか?それを考えることは僕にとって初めてのことでした。
でも、とても良かったことは、コロナ禍の時に撮影するのがどれほど大変なことかということをみんなが理解していたから、みんなとても辛抱強かったことです。みんなが協力してくれました。
――あなたの映画を観るのを楽しみにしている方々にメッセージをいただけますか?
ハオ・ズン:僕の映画を観てくれて本当にありがとうございます。僕の映画を観て、少しでも自信をもってもらえたらいいなと思います。
あなたは独りぼっちじゃないし、あなたの声を聞いてもらえるんだと感じてもらえることを願っています。
『最後のチュパカブラ』
監督:ジェシカ・メンデス・シケイロース
『最後のチュパカブラ』の舞台は、⽂化が存在しなくなった世界。
伝統を守ろうと奮闘する孤独なメキシコ系アメリカ⼈の⼥性が、知らず知らずのうちに古代の⽣き物を呼び出してしまいます。
ソノラの原住⺠とヨーロッパ⼈の混⾎家系出⾝のメキシコ系アメリカ⼈⼥性の脚本家/監督ジェシカ・メンデス・シケイロース氏。
彼⼥の短編映画の数々は、75の映画祭で上映されています。
――この映画のアイディアは、どのようにして得られたのでしょうか。
ジェシカ・メンデス・シケイロース監督(以下、敬称略):『最後のチュパカブラ』のキャラクターの名前は、私の曾祖母のチャパにちなんで付けたのですが、特に曾祖母のチャパが100歳まで生きたことにインスパイアされたんです。彼女は100歳のお誕生日の5日後に亡くなったんです。
私の家族はずっと、メキシコ人であることを、メキシコ系アメリカ人の家族であることを、とてもとても誇りにしてきました。元々アリゾナ出身だけど、その土地にずっといたんです。(アリゾナ州はもともとメキシコの領土)
私は曾祖母が亡くなった後、彼女と一緒に25年間も生きていたのに、彼女から何も受け継いでいないということに気づきました。
そして、私たちの文化を知る機会を失ってしまったことにショックを受けました。だからこそ、私たちの文化を維持し続けるのは、私たちの責任だと気づいたんです。
私が、Disney Launchpadに何を提出するかを決目なければならなかった時、文化ついて考え始めました。
この国(アメリカ)で他文化というのは恐れられています。他文化を称賛することは、自文化の破壊だとも考えられているんです。
私がそれを描くベストな方法は、とても恐ろしい怪物を通して描くことでした。チュパカブラを通してそれを表現するために、この寓話と組み合わせたんです。
そして、私たち自身の文化を称賛することは、私たちがどういう人であるか、ということを表現したかったんです。
――2つの文化を持つアメリカ人として育てられたことは、どのように作品に反映されていると感じますか?
ジェシカ・メンデス・シケイロース:私は、メキシコ系アメリカ人であることが、私の人生をすごく濃厚にしていると思っています。また、私の家族の血筋が先住民だということで、ある時点で誰がどの土地を所有していて、どんな文化がその土地に入れ込まれたのかといった、自分や家族のルーツに昔から関心がありました。
それが現在、映像作家として自分が何者かということを問うことになるきっかけになったのだと思います。そしてそれが、私たちが映画を通して伝えられる最大のメッセージなんです。
メキシコ系アメリカ人ということが何を意味しているのかや、Latinx(ラテンアメリカ系住民)という大きな総称が何を意味しているのか、ということを私が包括的に描くことは不可能です。
私ができることは、私の経験や私の人生にある多重の文化をとても明確にして、これらのストーリーを人々と分かち合うことです。そして、そんな機会に恵まれたことは、とても幸運だと思います。
――チュパカブラはとてもキュートで、細かく作り込まれています。何で出来ているんですか?もちろんエフェクトもあると思いますが、どのようにチュパカブラを作ったのか話していただけますか?
ジェシカ・メンデス・シケイロース:チュパカブラは、ほとんどエフェクトを使っていないんです。チュパカブラというのは未知の存在なんです。それを表現するために、最高のパペット・メイカーを見つける必要がありました。
そこで私たちは、ニューヨークを拠点とするパペット・ヒープという会社と仕事をすることになりました。彼らの制作は、本当に素晴らしかったです。
私は、アレブリヘ(動物や実在しない動物などのメキシコの伝統工芸品)や、いろんな要素が混ざったスタイルや、文化的な要素をふんだんに含んだパペットに注目しました。
それらは、まるで木に見えるように作られています。パペットを動かす役者は、この、とても重いパペットを、いつも動かさないといけませんでした。
目と口には、実際に動かすことが出来る工夫がありました。尾は、木で出来たヘビに見えるように作られていました。
チュパカブラは、少しずつ、そして多くの他文化的要素で作られていて、メキシコとアメリカ南西部のパペット作りの土着のスタイルにとても似ているんです。
『イード』
監督:アクサ・アルタフ
イスラム教徒でパキスタン⼈の移⺠のアミーナは、イスラム教最大の祝祭”イード”の⽇、学校を休めないと知ります。
ショックを受けたアミーナは、イードを休⽇にするため署名活動を始めることに。
休⽇にはなりませんでしたが、すれ違っていた姉と再び⼼が通じ合います。
アミーナは新しい街を受け⼊れ、街の⼈々もまたアミーナを受け⼊れたのでした。
クウェートでイスラム教徒のパキスタン⼈とスリランカ⼈の両親に育てられ、多様性と普遍的なストーリーを描く、監督のアクサ・アルタフ氏。
USCの映画芸術学科を卒業しています。
短編映画『ONE SMALL STEP』は数多くの賞を受賞しているほか、2019年カンヌ映画祭ではアメリカン・パビリオンで上映されました。
――”Disney Launchpad” に選ばれた時、どう思いましたか?1,100人以上の応募があったそうですね。
アクサ・アルタフ監督(以下、敬称略):最初は信じられませんでした。クレイジーだったし、素晴らしく名誉なことだした。
ディズニー映画で、イードについてのストーリーを語ることは、私の子供の頃からの夢だったんです。それをすることが出来て、ものすごく感謝しています。
―― 子供のころからイード(イスラム教の断食明けの祭り)についての映画を作りたかったということですが、この映画のアイディアをどのようにして思いついたんですか?
アクサ・アルタフ:私は元々、移民についてのストーリーを語りたかったんです。これまでに私が観たすべての移民のストーリーは、移民が新しい居場所や文化を受け入れていく、というものでした。
同化(より大きな集団の文化や風習などを受け入れる過程)を描いていました。でも今はもう、文化や集団が私たちのことをもっと受け入れるという時代に来ていると思います。
だから私はこの映画で、ここにやってきた移民がその文化を受け入れつつ、逆に移民の文化も受け入れられていくということを描きたかったんです。
それは私にとって、とても重要でした。それがこのストーリーを語る原動力だったんです。
もう一つは、私がアメリカに引っ越してきた時、誰もイードについて知らなかったということです。新しい場所でとても孤独を感じました。
特に私は、家族と一緒に引っ越してこなかったから。だから私は、イードをもっとたくさんの人に知って貰おうとしたんです。だって、世界中にいる18億人ものイスラム教徒がイードを祝っているんですよ。本当に大きなお祭りだと思います。
だから、それがメジャーのマスコミに取り上げられないということ自体が、私にとってはクレイジーなことなんです。
――撮影はいかがでしたか?
アクサ・アルタフ:本当に大変でした。子供と撮影することに関しては法律があるから、撮影は限られた時間でしかできなかったんです。その上にコロナ禍のことが重なって…。
だから、さらにタイトなスケジュールになったんです。でもこのことは、私を監督として、とても成長させてくれたと思います。
監督って、事前準備がとても大切なんです。私はいつもプランAとプランBを持って撮影に挑んでいました。でも、コロナ禍の後は、プランCとプラン Dも持っていないといけないと、すごく思ったんです。
だって撮影現場では常に何が起こるか分からないから、念入りに準備しないといけないんです。例えば、5つのショットを撮影したいのに、2つのショットしか出来なかったりする。そしたら、2つのショットでストーリーを語らないといけなくなる。それを現場でどうするか判断を下さなくてはならなくて、凄くプレッシャーでした。
でも、そういう経験が私を強くしてくれました。監督業は、本で読んだりした知識じゃなくて実践が重要。だから、この経験は私をもっと強い監督にしてくれたと感じています。間違いなくね。
――どういうことをこの作品から受け取ってもらいたいですか?
アクサ・アルタフ:日本の皆さんに知ってほしいことは、私たちはみんな、両親や祖父母、マスコミ、教育などの偏見を通して、文化や宗教がどういうものかを見ているということです。
でも私たちはその偏見に対して、常に疑いの目を向けているべきなんです。そしてすべての文化や宗教を通じて、彼らの人間性を感じ取ってほしいです。彼らはあなたたちと同じなんです。
すべての人間にはあなたと同じように、大切なホリデー(祭日)がある。彼らにも、あなたたちと同じように、大事にしたい家族がいます。
私は日本の皆さんがこの映画を見て、前の世代から受け継がれてきたすべてのものに疑問を投げかけることを願っています。
そして私たちはこれから、誰のことも否定しない、みんなにとって平等な世界を作ることが出来ることを心から願っています。
”今”を映し出す監督たちの、心に響くメイキング映像を解禁
配信開始に先駆け、短編映画6作品のメイキングシーンが収められた特別映像を公開。
公開された特別映像では、短編映画6作品の監督たちが、コロナ禍でフェイスシールドとマスクを着用しながらキャストやディズニーのスタッフらと共に試行錯誤しながら撮影に挑む様子が映し出されています。
そこからは誰もが予想しえなかった困難な状況の中でも、夢を叶える強い想いと信念が伝わってきます。
「受け入れてもらえないことへの不安、それを共有できるようになれば、本当に大きな力になるんです」と。
そして6人の映像作家がそれぞれの作品に込めた想いも語っています。
映像作家のコメントも到着
また、同時に解禁された映像作家のコメントも到着。
人間とバンパイアの間に生まれた少女の悩みをコミカルに描いた『若きバンパイアの憂鬱』の監督アン・マリー・ペイス氏は、
「私はメキシコ系アメリカ人で、バイセクシュアルなんです」
と明かします。
この作品で描きたかったテーマについて、
「子どもの頃、2つのアイデンティティの間にいるように感じて、これらのアイデンティティのどこに属しているのかはっきりわからなくて、とても苦しみました。
私はそういうことを主人公の少女を通して掘り下げたかったんです」
そして、バレエや人形遊びが好きな中国人の少年と、その友達との友情の物語を描いた『リトル・プリン(セ)ス』の監督モキシー・ペン氏は作品の背景について
「僕は主人公のガブリエルみたいな子で、とてもフェミニンなものやピンク、プリンセスに夢中でした。
近所にすむ友達の父親から『モキシーは普通の子供じゃないから矯正する必要がある』と言われたとき、自分の父親は『あるがままの息子を愛している』と言ってくれたんです」
と、父親がすべてを肯定してくれた幼少期のエピソードがあったことを語ってくださいました。
映画ライター・よしひろまさみちさんが考える「Disney Launchpad」
ディズニープラスで始まった短編映画集「Disney Launchpad」は、若い映像作家の発掘事業を目的としたプロジェクト。
だが、もう一つの側面は、ダイバーシティとインクルージョンだ。
ファミリー向け作品の世界的ブランドであるディズニーが、このテーマに着手したことには大きな意味がある。
2000年代、ディズニー・アニメーションは大きく変わりつつあった。
宇宙のモンスターとロコの少女の友情を描く『リロ&スティッチ』やゲーム世界を舞台にプリンセスがアクションに挑む『シュガー・ラッシュ』など、例を上げればきりがない。
それまでのディズニー映画の定石は「プリンセスかそれに準ずる少女が危機に見舞われ、王子様かそれに準ずる男性が彼女を救う」という物語。
その設定を現代にアップデートするとこうなります、という例を、ファンタジー世界を舞台にして描いてきた。
この根底に流れるテーマは、ダイバーシティだ。世界には多様に満ちていて、善人もいれば悪人もいるし、持つもの持たざるものもいて、それに対する偏見や差別も当然のようにある、という世界観。
映画の主人公たちはそれらの困難を乗り越え、調和した未来へと導く道標として描かれている。
さらにいうと、その考え方もじつはすでに古いもので、『アナと雪の女王』以降はインクルージョンが強く打ち出されており、新作を観るたびに、マイノリティを含む「個」への温かな眼差しを感じるようになった。
これは、そもそもディズニーが「よそさま」を受け入れるようになったからだろう。
御存知の通り、06年からディズニーのファミリー企業となったピクサー・アニメーション・スタジオをはじめ、マーベル・スタジオ、ルーカスフィルムなどのビッグスタジオを次々傘下におさめてきたディズニー。
それぞれの才能を持つスタジオを受け入れる、というのは、いわば他から来た人を家族として招き、互いの⻑所を受け入れて高め合うコミュニティを形成するということだ。
このように会社がアップデートしているのだから、作品がアップデートしないわけがない。
「Disney Launchpad」では、新たな才能の発掘だけでなく、その作家たちの人種や文化も多様にすることで、どこにもカテゴライズされることがない個性を打ち出すことに成功している。
たとえば人とバンパイアのミックスとして生まれた少女を描く「若きバンパイアの憂鬱」では人種が阻む壁の空虚さ、「リトル・プリン(セ)ス」ではアジア的なジェンダー観が妨げる成⻑と友情などなど。
どれも現実社会で調和を妨げようとする旧来の価値観への問題提起がテーマ。
倫理的に間違っていない個性を伸ばす生き方を推奨しながらも、「よそさま」を受け入れられないことが、どれほど社会を狂わせているか。
そこに切り込んでいるのだ。
このメッセージは、世界の子どもたちを勇気づけ、古い価値観を持つ親の心を変える可能性を秘めている。
「よそさま」を受け入れて迎えた今のディズニーだからこそ打ち上げられた、変化へのチャンスだ。
“発見”をテーマに、ユニークな視点で描かれた6つの多様な物語。
“Disney Launchpad"プロジェクト「短編映画6作品」は、ディズニープラスにて2021年6月4日より独占配信開始です☆
-

-
フレッシュな高校生たちの熱い物語を描くドラマシリーズ!ディズニープラス『ハイスクール・ミュージカル:ザ・ミュージカル』
続きを見る
-

-
シー・モンスターの世界と美しい港町を舞台に“最高の夏”を描く!ディズニー&ピクサー映画『あの夏のルカ』
続きを見る
-
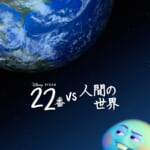
-
映画『ソウルフル・ワールド』の前日譚となるショートムービー!ディズニープラス『22番 VS 人間の世界』
続きを見る
© 2021 Disney